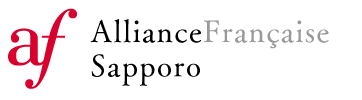フルコース料理と豊かなワインを堪能
札幌日仏協会恒例の「フランスワインとディナーを楽しむ会」が11月14日、メルキュールホテル札幌で開かれ、会員を中心に43人が参加しました。
冒頭、加藤利器理事長が、10月6日にチカホで実施したイベント「ボンジュール パリ」の成功に触れ、「今後も協会の活性化と会員の増強に取り組みましょう」と挨拶。「ヴォートル・サンテ」を唱和して開宴しました。
今年のメニューは本マグロのカルパッチョにはじまり、アンコウのロティ、道産牛フィレ肉のローストなど豪華な料理が用意されました。各料理にあわせて7種類のワインが次々と注がれ、参加者はボルドー、ブルゴーニュ産の芳醇な赤と白のワインと料理とのマリアージュを楽しみました。
抽選会では、協賛したグランヴァンセラーとアンビックスから各種ワインやホテルの宿泊券や入浴券などが提供され、当選番号が発表されるたびに、大きな歓声が広がりました。
終始、和やかな会は、江口修顧問の「日仏交流のさらなる発展・進化を」との呼び掛けで終宴となりました。
皆さん、良きクリスマスと年末年始をお過ごし下さい。
(理事長 加藤利器)
函館日仏協会10月例会で講演
函館日仏協会(若山直会長)の10月例会に招かれ、今年6月から7月にかけて約1カ月間、滞在したフランス第2の都市リヨンの魅力について会員の方たちにお話ししてきました。
例会は10月12日夜、西部地区にある五島軒本店で開かれ、会員30人が参加されました。
私はまず、リヨンがかつて絹織物の世界一の生産地として知られ、クレディ・リヨネに代表される金融都市としても発展してきた現状を説明しました。
- 函館日仏協会10月例会での講演会
引き続き、絹織物産業の衰退に伴い、新たに「美食のまち」として成長を遂げ、ポール・ボキューズやトロワグロ兄弟など伝説の料理人を数多く輩出、ミシュランの星付きレストランがひしめき合っている話を紹介すると、みなさん興味深く聞き入ってくれました。
また、日本との関係では永井荷風や遠藤周作が滞在し、「ふらんす物語」や「白い人」(芥川賞受賞作)の舞台となったことに触れ、スライドを使ってそれぞれの足跡を振り返りました。
なお、アリアンス・フランセーズの「アラカルト・セミナー」で秋学期から3回にわたり、「リヨンの魅力を探る」と題してお話しをしています。よろしかったら受講ください。
(理事長・加藤利器)
「ボンジュール パリ」楽しく賑やかに開催
札幌日仏協会は10月6日、パリの魅力をトークと音楽、写真で伝えるイベント「ボンジュール パリ」を札幌の地下歩行空間に直結したD‐LIFEPARKで開催しました。
今年夏にパリで100年ぶりにオリンピックが開かれたのを機に、フランスへの興味や関心をさらに広げて会員を増強しようと、札幌アリアンス・フランセーズの協力を仰いだ初めての企画でした。
- オープニングライブ演奏
会場では音楽グループ「エスポワール」、札幌手風琴倶楽部、マルカートのライブ演奏と、楽しいトークショーが交互に織りなす形で進行しました。
-
オープニングライブ演奏
エスポワール (高島桃子/山本舞/山下裕子)
-
オープニングライブ演奏
札幌手風琴倶楽部
-
ライブ演奏 マルカート
(タテヤマユキ)
トークではまず、私(加藤)とアリアンスの講師マリオン・ベガスさんが、日本人にとって憧れをかきたてるフランスの魅力を語り合いました。引き続き、アリアンス院長の二コラ・ジェゴンデさんが最新のパリのお勧めスポットを紹介。
-
人々の魅力を集めるフランス、パリを語るトーク
(加藤利器理事長/マリオン・ベガス講師)
- パリで活躍する日本人、お店、スポットを語るトーク
北大大学院教授の村松正隆さんは「秋に読むフランス小説5選」と題して北海道書店ナビのライター佐藤優子さんと対談し、読書好きの聴衆の注目を集めました。
人気を呼んだのはフランス料理のシェフ南大輔さんのトーク。会員の平山陽子さんの質問に応じる形で、料理人を目指した自らの経歴を披露しながら、フレンチの奥深さを語りました。
-
フレンチの魅力を語るトーク
(シェフ南大輔/平山陽子理事)
-
秋に読むフランス小説5選を語るトーク
(村松正隆常任理事/ライター佐藤優子)
会場には会員が撮影したパリの街角や凱旋門、エッフェル塔、オペラ座などの珠玉の写真が展示され、イベントに彩りを添えました。
(理事長 加藤利器)
パリ祭の夕べ2024 快晴の青空の下 盛会のうちに終わりました
パリ祭の夕べは今年もフェアフィールド・バイ・マリオット札幌で開催しました。
昨年とはうって変わり快晴の青空の下、華やかな植栽が色づくホテルの中庭が会場となり、75名が参加。例年以上の賑わいとなりました。
- パリ祭の夕べ2024 会場風景
冒頭、古野会長(在札幌フランス共和国名誉領事)からのご挨拶と乾杯の唱和から始まり、
- 古野会長
厳選されたワインとお食事に舌鼓。楽団Tuttiのアコーディオン奏者高嶋さんの演奏が更に会場を盛り上げ、和やかな中で恒例の抽選会も開催。
- アコーディオンの伴奏でシャンソンを歌いました
加藤理事長の閉会の挨拶のあとも賑わいの余韻を楽しむために夜の街へ繰り出す方々も…。和気あいあいの2時間でした。
- 加藤理事長
来年も会場はフェアフィールド・バイ・マリオット札幌です。
黒田昭信先生による講和
2024年7月20日 「フランスの若者たちの日本〈 幻想 〉 ? ポップカルチャーの鏡の中で」
7月20日(土)、「パリ祭の夕べ」に先立ち、ストラスブール大学言語学部日本学科の黒田昭信准教授による講演、「フランスの若者たちの日本〈 幻想 〉 ? ポップカルチャーの鏡の中で」が行われました。黒田先生は、ストラスブール大学で博士号を取得され、20年近く、フランスにて日本語や日本学の教育に携わっています。
お話は、日本に様々な〈幻想〉を抱くフランス人大学生が、しばしばなぜそうした〈幻想〉を抱き続けてしまうのかを、現場での教育体験をもとに分析なさるものでした。黒田先生はこの問題を、フランスでの外国語教育における相対的な地位の低さや、大学入学に際しての選抜システムと関連付けつつ説明なさいました。お話は時に厳しい現実に触れるものでもありましたが、最後に、日本の様々な〈現実〉に触れようとするフランス人大学生の優れた発表の紹介もあり、希望を感じさせるものでもありました。講演の後も、日本の教育との比較などに基づく活発な質疑が交わされました。
常任理事 村松正隆
「第16回パリ祭記念ペタンク大会」のご報告
1年間のご無沙汰でした。札幌ペタンク協会会長の中村です。毎年恒例の「パリ祭記念ペタンク大会」についてご報告します。
- 開会時の記念写真
今年は、本国の「7月14日」より1週間遅れの21日に「札幌市西区農試公園」屋外コートで開催いたしました。
当日は、加藤理事長、吉田事務局長、前理事長の江口様にも参加頂き、大会を盛り上げていただきました。折よく大会前日に開催された「パリ祭の夕べ」での宣伝と参加依頼の言葉が功を奏したのか、札幌アリアンス・フランセーズの若い先生とご友人に参加頂き、例年参加の元理事のデュボワさん含め、フランス人3名が国際色豊かなイベントとして盛り上げてくれました。普段、顔を見慣れた者同士で少しマンネリ化したゲームに甘んじているペタンク協会の会員には嬉しいサプライズでした。
- 優勝カップ返還
- 計測中
- 入賞者
大会冒頭の主催者挨拶(加藤理事長)の後、前年度優勝チーム(「池田協会嵯峨チーム」)から優勝カップの返還がなされた後、2ブロック各5チーム編成で総当たりの予選を行い、上位2チームによる決勝トーナメントを行いました。今回は「アルテラ」チームが優勝でした(トリプルスの内、2名が札幌協会会員、1名が道東「美幌協会」からの応援参加)。このように、北海道全体で札幌日仏協会主催の大会が支えられているのは嬉しいことです。地方大会に出向くと、「今度のパリ祭はいつ?」と、よく声を掛けられます。
本年は「パリオリンピック」の年ということで、地元のテレビ局(テレビ北海道)が取材に訪れました。フランス発祥の球技「ペタンク」を取り上げ、特に北海道(池田町)と札幌における競技の現状と普及の歴史等について紹介したいとのことでした。取材担当者もプレーに加わりましたので、ペタンク競技の面白さをお茶の間に伝えて下さることでしょう(※)。
来年、また新たな様相で開催できることを期待しております。
※7月31日(水)17:15からのニュース番組で放映
理事 中村寿司
追悼 原子修先生
原子修先生が亡くなられた。思うにつけコロナの三年間は先生にとって切歯扼腕の時間だったことだろう。ようやく縄文文化がうねりとなって先生の詩的世界が大きく広がるチャンスに動くことを禁じられたのだから。
協会の重鎮であられた先生と知り合うきっかけは札幌日仏協会創設にさかのぼる。設置の準備で、詩人の橋本征子先生とお会いし小樽の繋がりで親しくお話しするうちに、征子先生のパートナーが原子先生でいらっしゃることを知り、北海道詩壇をリードするお二人にお付き合いいただけることになった。
お二人とも、日本の詩人の常として、大学などに職を確保されて創作にいそしまれていたが、そんな折、原子先生がいらした札幌大学に文化学部が新設され山口昌男さんが学部長として迎えられた。彼の招きで翌年今福龍太さんが教授で赴任したが、この二人の偉大な人類学者との出会いが大きな刺激となって原子先生の詩想にインスピレーションを与え、『原郷創造』に至る縄文詩群創作過程のトリガーを引いたのではと今にして思う。その後、わたしが事務局長、理事長を務めた時期には、征子先生を交えて三人でフランスとの交流で楽しい苦労を重ねた。フランスで編まれる日本詩のアンソロジーにお二人の詩が選ばれることが多く、その仏訳をめぐって意見を交したり、縄文詩劇のフランス上演実現の戦略について知恵を絞ったことが懐かしく思い出される。さらには、協会創立20周年を記念したピエール・クルチアードピアノコンサートで先生の自作朗読にピアニストが即興演奏で応えたデュオも忘れ難い。
- 朗読する原子氏
- クルチアード氏とのデュオ
北海道をまわると原子先生の詩碑がたくさん見つかる。ご本人も覚えていらっしゃらないほどだが、それは先生がいかに北海道を愛され、ご自身の詩の源泉となされたかの証左であろう。そしてそこからフランスをはじめとした世界に直接響く詩〈うた〉を生み出されたことは特筆に値する。あらためて先生の偉大な詩業に思いをはせながらご冥福をお祈りしたい。
(顧問 江口 修)
札幌日仏協会理事会・総会開催 年度方針は「人心一新、組織力を強化して基盤固めを!」
札幌日仏協会の理事会・総会が2月10日、メルキュール札幌で開かれ、2023年度の活動報告・会計報告と24年度の活動計画・予算計画など議案6件が全会一致で承認されたことをご報告いたします。新年度は常任理事、理事の多くが入れ替わり、人心を一新して、新たな体制での一歩を踏み出しました。
会に先立つ理事会には古野重幸会長をはじめ10人が出席し総会に諮る議案6件を審議。また札幌アリアンス・フランセーズの2023年の決算報告書も提出され、ニコラ・ジェゴンデ院長から受講者の確保をはじめ経営環境が安定している現状について説明がありました。
続く総会には会員21人が出席。吉田雅典事務局長の議事進行により、規約改正、役員改選を含む議案6件が原案通り可決されました。
首記のとおり「人心一新。組織力を強化して将来に向けた活動基盤を固める」を年度方針に掲げ、新体制による協会の活性化と新規イベントの推進を参加者全員で確認しました。
さて、この日の総会には来札中の名古屋アリアンス・フランセーズ院長のオリヴィエ・オルティズさんが出席されました。オルティズ院長は来賓挨拶で、現在、世界中に850校を展開するアリアンスの現状に触れ、「(850校は)規模も資金も全く異なり、それぞれの顔を持つが、(フランス語・文化を通じた)新たな価値観を創造・発信する使命と目的を共有している」と語り、連帯と結束を呼び掛けました。
総会の後は、会員の親睦を図る懇親会が催されました。
冒頭、私(加藤)から、昨年7月にパリで開かれたアリアンス・フランセーズ創立140周年世界大会への出席報告をさせて頂きました。エリゼ宮でマクロン大統領主催のレセプションが開催されるなど、フランス政府がいかにアリアンスを重視しているかについて紹介し、皆さんは大きな関心を示して下さいました。
会場では古野重幸会長や前川二郎副会長をはじめ、新しく役員に就任された方たちを囲んで話の輪が広がり、最後は理事から常任理事に就任された川中加津子さんの乾杯で宴を締めました。 (理事長・加藤利器)
なお、新たに就任した役員は次の通りです。
▽常任理事 下村晴信(社会医療法人社団三草会、クラークウェルネスクリニック)、柳澤重毅(ITコーディネーター)、川中加津子(元川中スポーツ代表取締役)
▽理事 原田彦エ門(北海道日産自動車代表取締役社長)、中村督(北海道大学大学院法学研究科教授)、平山陽子(office vivace代表取締役)、伊藤実枝子(コンフィ代表取締役)、高橋康子(東京海上日動火災保険)
「フレンチディナーを楽しむ会」を4年ぶりに開催
札幌日仏協会の年末の恒例行事だった「ソムリエとフランスワインを味わう会」が装いを新たに「フレンチディナーを楽しむ会」となり12月9日、コロナ禍を経て、4年ぶりに開催されました。会場のメルキュールホテル札幌には再開を待ち望んでいた会員を中心に42人が参加し、おいしいワインと道産食材を使ったフルコースのメニューを堪能しました。
久し振りの開催ということで、食事の前にはスペシャルトークを企画しました。講師はuhb北海道文化放送のお天気キャスターとして活躍されている菅井貴子さんで、「世界の空から見えてくる地球温暖化」と題して1時間にわたり講話を頂きました。
引き続き、食事会の開宴です。理事長の私(加藤利器)の開会挨拶に続き、前川二郎副会長の音頭で「サンテ」と唱和すると、この日のために用意した特別メニューが次々とテーブルへ。
(理事長・加藤利器)
函館日仏協会の11月例会で講演 理事長 加藤利器
函館日仏協会(若山直会長)の11月例会が11月24日(金)夜、五島軒本店で開かれ、昨年10月に続いて、函館の皆様の前で講演する機会を頂きました。
今夏、私はパリで開催されたアリアンス・フランセーズ(AF)世界大会に札幌を代表して参加し、世界131カ国から集まった仲間と交流してきました。マクロン大統領ともエリゼ宮(大統領府)で催されたレセプションでお会いしたことを若山会長にお話ししたところ、「ぜひ函館の会員にフランス滞在記と題して講演してほしい」と依頼があり、今回の訪問となりました。
講演は『函館とフランスを結ぶ深い絆』(Les liens profonds entre Hakodate et la France)と題し、AF世界大会の内容を中心に、函館日仏協会とフランスとの交流の歴史にテーマを広げて、滞在中に撮影した100枚の写真を使ってお話ししました。
アリアンス世界大会については、すでに当HPでもご報告しておりますが、世界に拠点を置くアリアンスが、単にフランス語を学ぶ場を提供するだけではなく、公平性と多様性を尊重しつつ、フランス独自の文化を世界に発信し続ける役割を果たさなければならないー。こうした世界大会の理念と精神を強調しました。
続いて、私はアリアンス世界大会後、約30日間にわたる自らの国内旅行について語りました。
私が訪れたのは、ロワール川河口の港町ナントと南仏アヴィニョン近郊のオランジュというまちです。旧友と再会するための旅でしたが、実はいずれも函館日仏協会の取り持つ縁で知り合った方たちでした。
偶然にも2人の名前はクロードさん、年齢は76歳です。
- ナントのクロードさん
- オランジュのクロードさん
(私は北海道新聞の函館支社報道部に勤務した時にこの報道に携わりました)

ナントと函館の姉妹都市
の動きを報じる
北海道新聞の記事
フランスの地方に住む人たちと函館の間に結ばれた交流の絆が、色褪せるどころか、時を経て、逆にくっきりと蘇る姿をつぶさに見て、私は感動しました。世界で悲惨な戦争が起きている時代に、真の平和とはこうした小さな友情の積み重ねによってこそ得られるのではないか。こんな思いを強くしたのです。
その意味で、函館日仏協会が果たした草の根の交流には、深い尊敬と敬意の気持ちを抱いております。私どもの協会も、フランスに向けて情報を発信し、フランスの市井の人たちと交流を深める活動ができないか。函館の皆さんと集合写真に納まりながら、こんな思いに駆られた、印象深い「函館旅」でした。
*講演の写真は函館日仏協会の佐々木慶一理事が撮影してくれました。佐々木さんは武蔵野美術大学在学中にパリ国立高等美術学校に留学した経験があり、金沢美術工芸大学大学院(修士)を経て、函館に帰郷して創作活動を続けています。